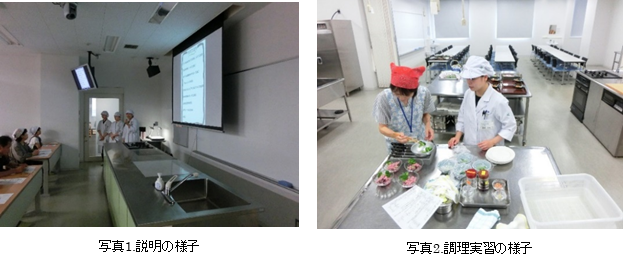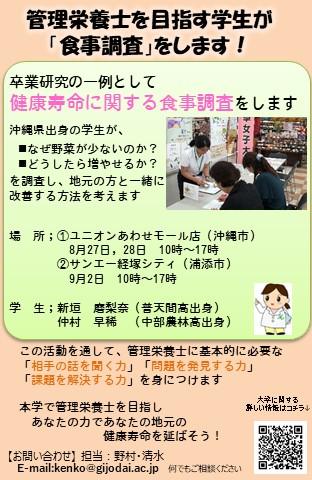ゼミ研究・活動
第3回『健康寿命を延ばす食教室』を開催!
「健康寿命を延ばす」をテーマに第3回食教室を9月10日(火)に開催しました。
今回は、3名の男性の方も参加して下さいました。男性の方は、料理教室という行事に参加することが初めてだとおっしゃっていましたが、最後には「とても楽しかった」「美味しかった」などのお声もいただくことができました。
今回の教室では、「だしの効果と利用方法」と「水溶性食物繊維」の2つに絞ってお話しました。
普段捨ててしまうような「野菜くず」を利用した「野菜だし」を使ったスープや煮物を食べていただきました。野菜のヘタや茎などからも「うま味」が出て、調味料を減らしても美味しく食べられるということを実感していただきました。鰹・昆布だしは購入しなければなりませんが、野菜くずは廃棄する部分を用いることができ、比較的作りやすいので「家でもやってみよう」と思われる方が多かったです。
次に、食塩の吸収を遅らせる水溶性食物繊維についてお話しました。食塩量を減らすことは簡単なことではないので、ご家庭でも実施しやすいような「普段の食事にプラス〇〇」という形でご紹介しました。
例えば、納豆ごはんや味噌汁にオクラ、なめこ、わかめなどの粘り気の強い食品をプラスすることで、水溶性食物繊維を簡単に摂ることができます。どれも身近なもので出来るので、「普段の食事にプラス〇〇」という意識を高めて高血圧予防につなげていただきたいです。
食教室終了後、アンケートに答えていただき、「毎日の料理に活かしやすい」「とても勉強になった」などの意見を多くいただきました。
教室を運営し、参加された皆さんからご意見をいただくことで、「相手に寄り添った考え方」「伝える力」「コミュニケーション能力」を学ぶことができました。この経験を今後につなげていきたいです。
最後に食教室にご参加いただいた山県市の皆様、食教室を開催する機会をいただいた山県市健康介護課の山田佐知子先生、誠にありがとうございました。(藤田研究室 山崎・吉田)
人に伝えるってむずかしい!!!
令和元年からだ改善プロジェクト第3回目を実施しました。まず、前回の補足としてお菓子のエネルギー量や炭水化物量を説明しました。その後、今回のテーマであるカルシウムとビタミンDについて知ってもらい、それらを多く含む献立を参加者の皆さんと一緒に調理実習をしました。内容がより分かりやすく伝わるように動画を作成したり、説明するときの資料や話す速度、言葉使いなどを考える中で人に正しい知識を正確に伝えることの難しさを実感しました。
調理実習では、参加者の方に調理を通して野菜の加熱前と加熱後の量の変化や家庭ではしないような調理法、マヨネーズの量など知ってもらいたいことが多くありました。そのため、参加者の方がスムーズに実習できるように、先に自分たちで下処理をしたり、細かいレシピとは別に実習で行う手順だけを記載したレシピを作成したりしました。実習中には、「マヨネーズはこんなに少なくていいんだ」、「野菜はこんなに少なくなるんだ」などの声がきこえ、伝えたいことが伝えられたと感じました。一方で、調味料の準備不足があったり、手伝ってくれる同じ研究室のメンバーへの情報共有ができておらず、臨機応変に対応してもらうことがありました。そのため、時間に余裕を持った計画を立てて実行していくこと、気づいたことや受けたアドバイスを記録し、忘れていることはないか何度も確認していくことが大切だと学ぶことができました。参加者の方からは、「炭水化物を摂りすぎていたことが分かった」、「塩分の使い方について参考になりました」、「学生にわからない所を聞いたり、一緒にアイディアを出したりして話せたのが楽しく、勉強にもなりました」等のご感想をいただくことができ、参加者の方が楽しんで学ばれていたことが分かり、やってよかったと思いました。次回のセミナーでは反省点を活かし、より良い内容になるよう工夫したいと思います。(笠井研究室 今井 茜)
沖縄研究活動スタート
4月から準備をしてきた現地調査が始まりました。
8月27日,28日 10時~17時 フレッシュプラザユニオンあわせモール店
9月2日 10時~17時 サンエー経塚シティ
で沖縄の皆さんが健康でいられるために、野菜摂取に関する調査をしています。
朝から足を止めて、ご協力いただきました。
『野菜?面倒だから食べないね〜』と答えてくださったり、
『あちさんや~(暑いですね)。頑張ってね~。』と声をかけていただいて、頑張ってます!(藤田研究室)
今年も沖縄で調査します!
私たちは、「沖縄県の健康寿命の延伸」をテーマに卒業研究に取り組んでいます。
沖縄県の健康に関する問題と食生活について文献で調べ、野菜摂取量が少ないこと、脂質摂取量が多いこと、飲酒量が多いこと、喫煙者が多いこと、これらに関連して動脈硬化や高血圧といった生活習慣病や肝硬変が多いことがわかりました。
そこで
・なぜ野菜をあまり食べないのか?
・どう工夫したら野菜摂取量を増やすことができるか?
に問題を絞り、沖縄に戻って調査をします。
そして、それらを解決するための方法を地元の方々と一緒に考えます。
課題を解決するためには、その原因を探る必要があります。
その原因に合わせた解決方法をみなさんと一緒に考えることで、実行しやすい改善策を提案していきます。(藤田研究室)
第2回『健康寿命を延ばす食教室』を開催!
「健康寿命を延ばす」をテーマに第2回食教室を7月23日(火)に開催しました。
適塩生活の基盤をつくるには、子どもの頃からの食育が大切です。また、子どもから親世代に発信してもらうことも効果的です。そこで、高血圧予防を関連付けるために、野菜を摂取する意味を伝え、野菜の一日の摂取量を350gに近づける調理法や工夫を学んでいただきました。
今回の献立のポイントは、包丁をあまり使わず、子どもでも安全に楽しく作れるメニューにしました。そして、野菜を効率良く食べてもらえるようなものにしました。調理した「なんちゃってナン」、「さばとたっぷり野菜のドライカレー」、「きらきらスイカゼリー」は子どもたちがとくに喜んで食べてくれました。ドライカレーは野菜をフードプロセッサーで細かく刻むことで、嫌いな野菜を無理なく食べられる子どもが多かったです。保護者の方もそれを見て喜んでおられ、また、肉ではなく魚を使うことに驚いておられました。ナンはこねて伸ばして、自分の好きな形を作っていて楽しそうでした。そのため、一番人気のメニューとなりました。
最後にアンケートを親子で書いていただき、「メニューが多くてちゃんとできるか心配だったが、みんなで分担してできたのが良かった」、「これなら家でも簡単に子どもと作れそう」、「嫌いな野菜を食べられた」などの意見が多かったです。
第3回目の食教室を9月10日に開催します。第2回目のアドバイスや改善点を活かして、より良い食教室にしたいです。(藤田研究室 山崎・吉田)