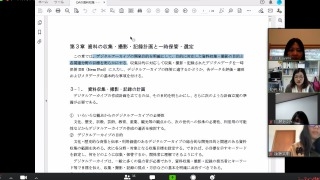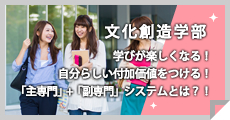授業レポート
遠隔授業を紹介します!「計画と資料の収集」中編
2年生用のデジタルアーカイブの必修科目「計画と資料の収集」の第3回の遠隔授業の中編をアップいたします。
(3)振り返りが終わり、本日の内容に突入!
今回はデジタルアーカイブを作成する上でカギになる「資料収集のための計画を立てること」について学びました。
本学オリジナルの「デジタルアーカイブの資料収集・撮影・記録の基礎」というテキストを使って説明を受けます。
①デジタルアーカイブの目的は?
②みんなに必要とされるデジタルアーカイブとは?
③資料はどこまで集めたらいいか?(時間や予算)
④資料をどのように集める?(デジタル化の方法、利用許可についても)
を学びました。
ここがポイント:オリジナルテキスト
岐阜女子大学は専門資格「デジタルアーキビスト」発祥の地で、授業もオリジナルカリキュラムを構成しています。
そして長年のデジタルアーカイブ実績をもとに、オリジナルテキストもたくさん作成しています。
オリジナルテキスト・・・つまり岐阜女子大学でのみ入手可能ということです!
この授業で使っている「デジタルアーカイブの資料収集・撮影・記録の基礎」もそうです。
学生には事前に郵送済みですが、本学で作成=テキストデータを持っている ということで
グループウェア「サイボウズ」でPDFデータも渡すことができます。
つまり、大学が閉鎖になり、4月に大学へ一回も行っていなくても、第1回の授業からテキストを使った授業ができました。
手元で冊子のを見たり、iPadでフルカラーのデータを見たり、学生は思い思いに活用しています。
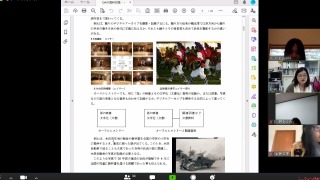
(4)例を紹介して学びを深めよう!
本学で行ってきたデジタルアーカイブを用いて、①~④について学びを深めていきます。
今日はデジタルアーカイブ専攻>デジタルアーカイブ・ラボ にある「長良川デジタル百科事典」を使いました。

(5)質問タイム!
難しい内容だったので、質問を受け付けました。
「とりあえずは大丈夫」とのこと。
このあと実習を行うので、そこで具体的な疑問が出てくるでしょう。
中編はここまで、後編は近日中にアップします。
次は実習に入ります!
遠隔授業を紹介します!「計画と資料の収集」前編
デジタルアーカイブ専攻では4月9日の前期開講日から遠隔授業がスタートし、
もう丸2週間が経過しました。学生もZOOMの授業にすっかり慣れた様子です。
本日(4月24日(金))の3限は、2年生用のデジタルアーカイブの必修科目「計画と資料の収集」の第3回の講義がありました。
その講義の流れをご紹介!
「計画と資料の収集」ってどんな授業?
「計画と資料の収集」は専門資格「デジタルアーキビスト」を取得するために必ず単位を取らないといけない授業です。
デジタルアーカイブは、記録→保存→活用→評価→(最初に戻る)を行いますが、この授業では「記録」するのに必要な「資料収集のための計画を立てること」と「資料の収集方法(デジタル化)」の習得を目標としています。
デジタルアーカイブの出発点にあたる、とっても大切な授業です!
(1)授業開始!まずは出席確認
先生の点呼のもと、学生はマイクで答えます。
学生は、スマホやiPad等のタブレット端末、ノートPCでZOOMに接続しています。
(2)先週の授業内容と課題を振り返ります
先週は、デジタルアーカイブに必要な撮影方法を学びました。
先週の課題は、いろんな対象物に対してどんな撮影方法が適しているのか、何に注意すべきかをまとめて提出です。
課題はGoogleフォームで提出しています。Googleフォームを画面共有してみんなの課題の内容を確認します。
みんながどのようにまとめたのか、何を注意点として書いているのか、
自分とは違う意見を見れるのは、とても参考になります。
Webで課題を提出して終わりではなく、課題に対しての評価を学生に伝えるなど、遠隔授業になっても双方向型の学修になるよう心掛けています。
とても長くなりましたので、続きは近日中にアップします。
次は、(3)振り返りが終わり、本日の内容に突入! です。
遠隔授業がはじまりました
新型コロナウイルスの影響で大学閉鎖中ですが、
4月9日から前期開講に合わせて、遠隔授業がスタートしました。
本学で使用しているグループウェア「サイボウズ」、
インターネットでTV会議ができるクラウドサービス「ZOOM」、
これまで資料や授業動画などを蓄積してきた「e-learning」
などを使って、授業を行っています。
デジタルアーカイブ専攻では、大きなトラブルなく開始することができました。
授業の様子です。みなさん元気そうで安心しました。


遠隔授業に参加した学生に感想を聞きました。
・家にいるのに友達が近くにいる気がして不思議な体験でした。
・PowerPointは見やすくて、大学で直接授業を受けるのと変わらなくて安心しました。
・通学にかかる時間とか関係なく授業を受けれて、遠隔授業のメリットを体感しました。
・自宅だとやる気が出ないかなと思ったけど、授業のあとすぐに復習ができたりと自分のペースで集中して学習できました。
・本当は自宅待機で無駄になるはずだった時間が、授業を受けることができてうれしかったです。
・顔が見れるのが良かったです。久しぶりにみんなの元気な顔が見れてうれしかったです。
これからしばらくは遠隔授業が続くと思われます。
遠隔授業でも変わらない学びを提供していきます。
金沢⇔岐阜で卒業研究☆
岐阜女子大学には、岐阜県出身の学生さんのほか、沖縄県や静岡県、富山県など全国各地から学生さんが入学しています。
岐阜から離れた地域出身の学生さんにとっては、帰省中には、先生と一緒に研究したり学んだりすることが難しい面もありますが、三年生から大学での学びの集大成として行う卒業研究では、自宅に帰省中でも、ウェブ会議システムZOOMを用いて、先生と研究について相談したりしています。
金沢と岐阜でも、研究について話し合ったり、模擬発表会を開いたりがスムーズに出来ています☆
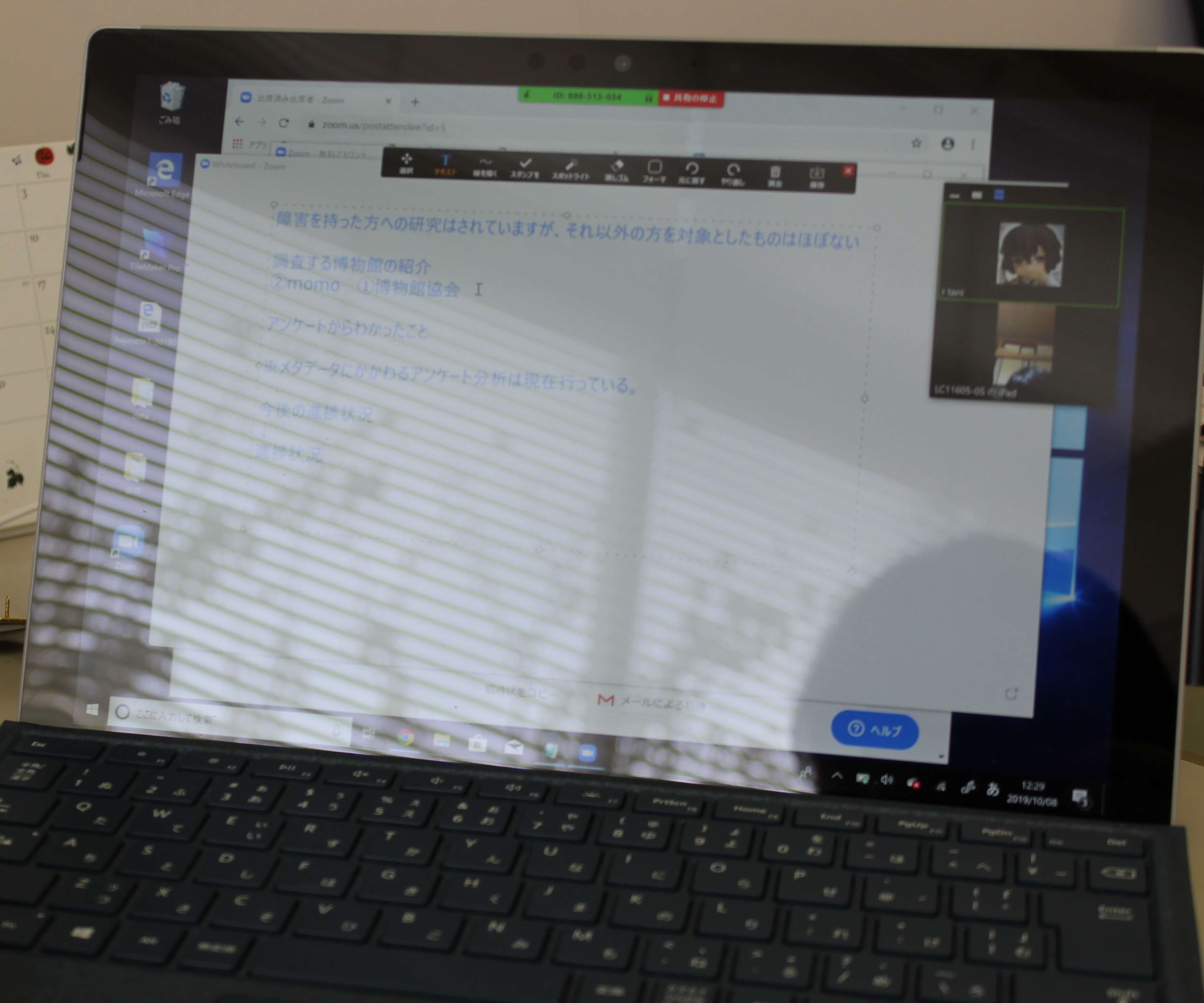
デジタルアーカイブ+観光コラボ~御鮨街道の記録~
岐阜女子大学は岐阜市にある大学なので、地元岐阜市の歴史的文化財など地域資源のデジタルアーカイブやそれらを活かした観光活動について学ぶことができます。
今年から、「岐阜市デジタルアーカイブ」の一環として、岐阜市内に残る街道の一つ、「御鮨街道」のデジタルアーカイブをはじめました。
まずは、「御鮨街道」のはじまり(起点)周辺について、実際に歩きながら学ぶため、まち歩き実習を行いました。
まち歩きの案内は、岐阜市社会教育課の横田宏先生。
一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社のご支援もいただきました。

今日はブラタモリ風にいきますね、と横田先生。
「御鮨街道」とは、江戸時代に岐阜の特産品として鮎の熟鮨を幕府に献上するときに使われていた街道で、「岐阜街道」、「鮎鮨街道」などとも呼ばれています。
歴史的なまち並みでありながら、現在も主要な道として使われています。
横田先生から、建物や街道の見方のアドバイスを受けたり、豆知識を伝授していただいたりしながら、進みます。


横田先生の解説をiPadでメモメモ・・・
岐阜女子大学の前理事長(4代理事長)でもあった岡本太右衛門邸で解散となりました。

歴史的な町並みの一つでもある「御鮨街道」のデジタルアーカイブには、撮影をしたり、撮影したものが何であるのかなどの説明を考えて付けたりすることが必要ですが、たとえば観光客に対してなどの活用方法を考えることも大切です。
つまり、デジタルアーカイブの視点、観光の視点などが必要といえます。
岐阜女子大学には、デジタルアーカイブの他にも、観光や国語を学ぶ専攻があり、今回の参加学生も、デジタルアーカイブを学ぶ学生だけでなく、観光を学ぶ学生も、国語や書道を学ぶ学生も参加しました。
一つの分野の学びだけでなく、デジタルアーカイブ、観光、国語、書道など様々な学びができるのも、岐阜女子大学の特長です。