健康・医療
食品衛生学実習・手洗い実習
調理や食事の前に手を洗っていますか。「は~い。もちろんです」という返事が聞こえてきそうです。でも、本当に正しく洗浄できているのでしょうか。
食品衛生学実習では、食品の安全を守るための実践的な方法を学びます。正しい手洗いに関する実習もその一つです。
紫外線があたると蛍光を発するクリームがあります。それを手に塗り、紫外線でクリームが光るのを確認してから手を洗います。手洗い後、再び紫外線ランプの下に手を入れると、洗い残しの部分が蛍光を発します。「あれ?」、たくさんの洗い残しがあるようです。
正しい手洗いは実は難しいのです。
実習では、このような手洗い実験を通して、「5ステップ6か所洗い」の正しい手洗いの方法を学びます。
以前、学生の皆さんと一緒にホテルの調理場を見学したことがあります。調理場へ入る前に手を洗いました。それを見ていた案内役のホテルの方から、「すごい!正しい手洗いが身についていますね。」と褒めていただきました。プロに褒められて学生達はニコニコでした。食品衛生学実習は、実践的な実習でもあります。

病院で活躍する卒業生を紹介します 卒業生Voice18
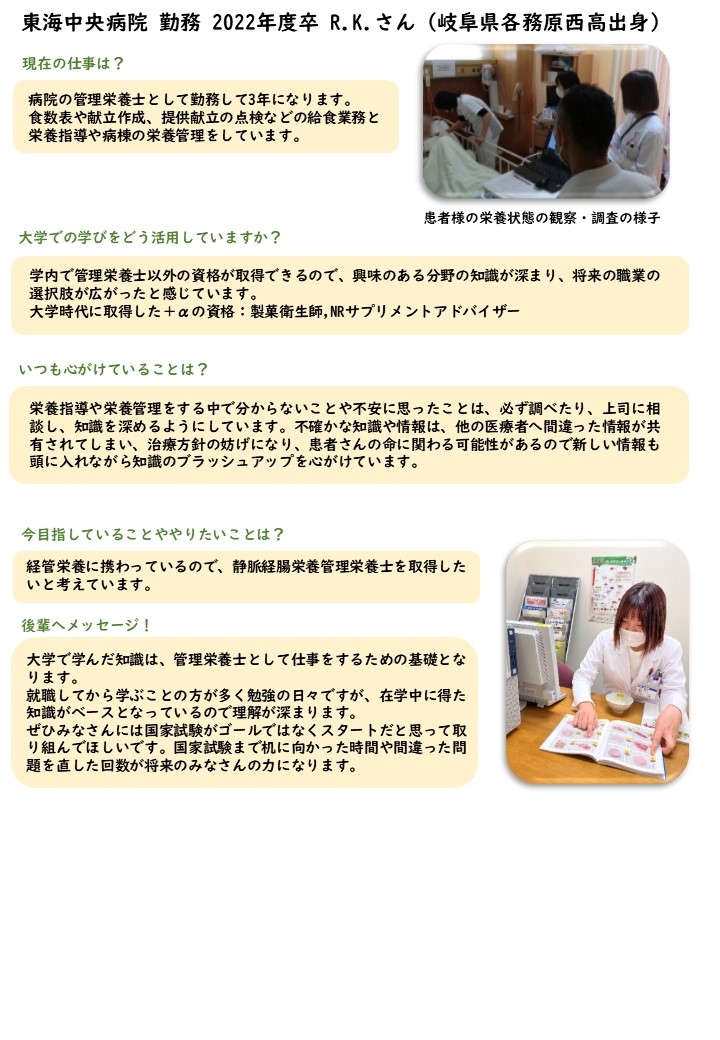
栄養士・管理栄養士+健康運動実践指導者を目指して
健康栄養学科では、運動の指導もできる栄養士・管理栄養士を目指して健康運動実践指導者の資格を取得することができます。健康運動実践指導者は、健康な人たちへストレッチなどの運動を指導するために役立つ資格です。病院・福祉施設の栄養士・管理栄養士、高校家庭科教員を目指す学生たちが受講しています。先日のエアロビックスダンスの対策講座では、先生に動きや注意点など指導いただきました。

福祉施設で活躍する卒業生を紹介します 卒業生Voice17

現地調査 in 沖縄(大宜味村)
沖縄県出身の管理栄養士を目指す私たちは、過去沖縄県で長寿地域1位であった「大宜味村」に現地調査に行ってきました。
塩屋ミニデイサービスに来られた皆様や、喜如嘉区長様、喜如嘉共同売店を利用された皆様からたくさんのお話を伺いました。
大宜味村では、みんなで食材を持ち寄り、調理して食事を囲みながら楽しく過ごすサンクェー(参食)が開催されていたそうです。近年ではサンクェーをされている地域はごくわずかになっているようです。
ミニデイサービスに参加された方々は、家の庭で家庭菜園をされている方が多く、「レタスやカズラが多いね。」、「ヨモギは庭に生えている物を摘んで、ボロボロジューシー(雑炊)に入れるよ。」などと教えてくださいました。翌日に「よもぎもち」を教えてくださるとのことで、お宅までお邪魔しました。優しい甘味で月桃の香りがする美味しい「よもぎもち」の作り方を教わりました。

沖縄県でも北部に位置する大宜味村は、沖縄県の西側の飲料水を供給する大切な地域であることや、大宜味村でも喜如嘉地区は糸芭蕉の産地であり、芭蕉布の唯一の生産地になっていることを教えていただきました。喜如嘉区長様の幼少期には、行事の際にサンクェーをやったと良く大人から聞いたそうです。また川の魚やエビを獲ったことや、イグサの産地だったことなども伺いました。

また、集落ごとにある共同売店には、地域の方々が生活に困らないように食品から日用品までそろえられており、売店内は休憩できるようにいわゆるイートインスペースまでありました。地域の方との交流もでき、1日に何度も利用される方もおみえでした。そこで、サンクェーを最近されたという方にもお会いできました。
盛りだくさんのことを伺ったので、これからまとめて論文にします。
本調査にご協力いただきました大宜味村観光協会事務局長様、大宜味村社会福祉協議会事務局長様、喜如嘉共同売店様をはじめ、インタビューにお答えいただきました塩屋ミニデイサービスご利用の皆様、喜如嘉区長様、喜如嘉共同売店にお越しの皆様に、厚くお礼申し上げます。(藤田研究室)
I.I(小禄高校出身)
A.N(沖縄工業高校出身)










