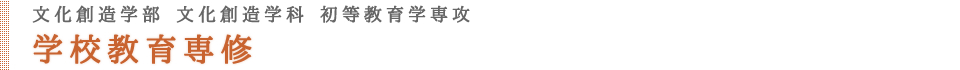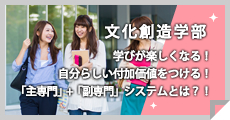オープンキャンパス
夏のオープンキャンパス・「おいしいぶどう」そして「ドローン」!
この夏のオープンキャンパス、初等教育学専攻の体験授業は「ぶどうづくり」「ドローン」そして「子どもの心の不思議」をテーマにお送りします。
7/28のオープンキャンパスは、「おいしいぶどうづくりの秘密をさぐろう」と題して体験授業を行いました。まずは、その授業の様子です。
今回の授業では、小学校3年生の社会科の学習「農家の仕事~長良のぶどうづくり」を体験していただきました。参加いただいた皆さん、岐阜市長良のぶどうの味はいかがでしたか。
農家の方が自然条件(砂地)を生かして心を込めて作られたぶどうなので、きっと甘くておいしいと感じられたのではないでしょうか。「おいしいぶどうの秘密は"土(つち)"にあり! でした。
参加していただいた皆さんには、ぶどうを食べていただいたり、おいしいぶどう作りの秘密を考えていただいたりして、積極的に取り組んでいただきありがとうございました。
最後ののまとめで本学の3人の学生も話していたように、人々がその土地の自然条件(地形や気候)を生かして生活していることを理解していただけたらうれしく思います。
そして......、次回8/4のオープンキャンパスでは「プログラミングとドローンを使って小学校の教材を作ろう」をテーマにお送りします。
小学校でいよいよ始まるプログラミング。この授業は、ドローンで撮影した植物動画教材の製作と活用した理科の授業についての体験をします。
梅雨があけて暑くなってきました。自然環境に恵まれた岐阜女子大学にぜひ足をお運びくださいね。お待ちしています。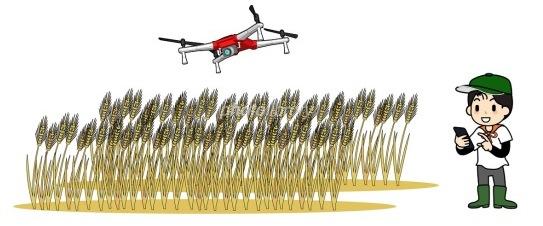
おいしい"ぶどう作り"の秘密 ~7/28オープンキャンパス体験授業
岐阜市を流れる清流長良川。市中央部から少し川上に向かった辺りに、今年もふどうの即売所がオープンし始めました。 岐阜市長良地区は以前からぶどう作りがさかんに行われています。毎年とても甘くておいしく育っており、シーズンに入ると広大なぶどう畑で多くの家族連れがぶどう狩りを楽しんでおられます。
さてさて。次回7月28日のオープンキャンパスでは、この長良地区のぶどう作りについての体験授業を行います。
小学校3年生から始まる社会科の学習では、自分が住む地域について調べたり実際に足を運んだりして学び、地域への愛情を深めていきます。 この授業では、実際に長良地区の子どもたち、住民の気持ちになって、ぶどう作りの秘密、魅力に迫っていただこうと思います。
夏休みに入った第1回のオープンキャンパス。(といっても講習等が続いているかもしれませんね。がんばって!) 自然豊かな岐阜女子大学に足を運んで、一緒に楽しく大学での学修を体験してみませんか。お待ちしています。

「言葉」...それはいったい何者じゃ? ~7/15オープンキャンパス授業
7月15日は月曜日ですが、祝日「海の日」です。高校生の皆さん、海とは正反対ですが、美しい山々に囲まれた岐阜女子大学で、大学生体験をしてみませんか?
この日、初等教育学専攻で準備している体験授業のタイトル、それは......
「言葉のお陰で・・・」、湯水の如くにしゃべっている言葉、それは何者か?
何やら不思議な響きのタイトルですね。先生になるために大学で学修する科目「国語科基礎」「自己表現」に関係するこの授業は、幼稚園・小中学校で"ながーく"先生としてたくさんの子どもたちの成長にかかわってきた初等の、国語科を専門とする教員が担当します。 その先生の「授業案内」の言葉を紹介しましょう。
毎日の生活は、言葉なくして成り立たないから、言葉は食事と同様に生きる必需なシロモノ。でも、言葉を食べるものほど気にしないままでいる。私たちの使う日本語に、「そうだったのか!」、とガッテンして貰いたい。
楽しく学べそうでしょ? ぜひ友人と誘い合わせて、岐阜女子大学に足をお運びください。お待ちしています。
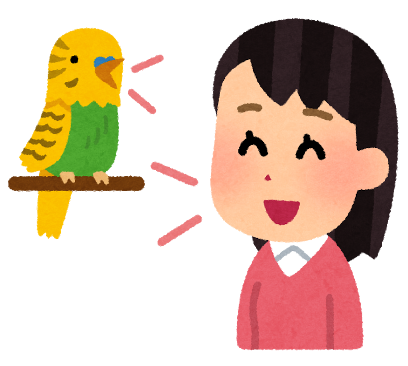
「目標に向かって努力することの大切さ」 ~オープンキャンパスで学びました
5/19のオープンキャンパスでは、「よりよい生き方を考える」体験授業を行いました。
幼児教育、学校教育を通じて、人としてよりよく生きるために22の大切なことを学んできています。
授業では、その中の一つ「目標に向けて努力すること」の大切さを取り上げ、子どもにもお馴染みの
「たなばたさま」「かくれんぼ」を作曲した下総皖一(しもおさかんいち)さんの生き方を通して学習しました。
授業の中で、本学の学生も登場、一人ひとり自分の将来の目標が叶うことを目指し粘り強く取り組んでいることを語ったり、保育士になったとき子どもの表情をみながら伴奏が弾けるように練習を続け実際に弾き歌いをしながらピアノ伴奏をしたりしました。

作曲家の下総さんは師範学校へ入学して初めてピアノに出会い、音楽の先生のように弾けるようになりたいと願って毎日練習を続けました。
その大切さを学んだわけですから、幼稚園や保育園、小学校の先生として、苦手な人も得意な人も、「さあ、夢に向かってがんばろう!」と子どもたちの前でピアノが弾けたら素敵だなという憧れの気持ちをかなえる本学の「ピアノスキルアップ講座」を体験しました。
一人ひとりの目標の実現に向けて応援する本学の一端を体感していただけたことと思います。
次回のオープンキャンパスは6月16日(日)です。今度は「紙しばいの魅力」に迫ります。またぜひお越しくださいね。お待ちしています。

自分の人生を輝かせるために!~5/19オープンキャンパス
5月19日のオープンキャンパス、初等教育学専攻では次の内容を用意して皆さんをお待ちしています。
《体験授業》 人生をよりよく生きるために~22の項目を知ろう!
《イベント》 心のこもった言葉のある しおりを作ろう
まず体験授業を紹介すると......
♫さーさーのーはー さーらさらー......幼稚園や小学校でよく歌いましたね。
ちょっと時期は早いですが「たなばたさま」のうたです。
また、♫かーくれんぼ すーるもーの よっとーいで...... こちらは「かくれんぼ」
小学校1年生の音楽の教科書にも載っている、これまたよく知られたうたですね。
これらは日本を代表する作曲家の1人である、下総晥一さんによって作られました。
この下総さんの生き方を通して、、音楽の内容も盛り込みながら、
人としてよりよく生きていくために必要な「22の内容」について、やさしく学びます。
さて、どんないったいどんな内容なのでしょうか。自分に生かせることばかりなので、お楽しみに。
そしてミニイベントでは、小さな色画用紙に心を動かす短い言葉を書いて、飾りもつけ、
ラミネートすることによって栞(しおり)を作成します。
大切な言葉を書き込んだ、自分だけの大切な作品づくりも、ぜひお楽しみください。