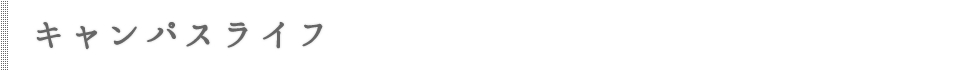自治会 アーカイブ一覧
鵜飼鑑賞会を行いました〜自治会〜
9月25日に長良川での鵜飼鑑賞会を行いました。コロナの影響によりここ数年開催できていませんでしたが、今回のタイミングでまた企画をし、多くの方に参加をしていただくことができました。
鵜匠さんによる説明を聞いた後、船に乗り、1300年以上の歴史を持つ鵜飼を間近で鑑賞し、暗闇に見える篝火の美しさと鵜匠さんの洗練された手縄さばきに感動しました。
ぎふ長良川鵜飼は国の重要無形民俗文化財に指定されている特別な伝統であるため、ぜひ毎年たくさんの方に経験して頂きたいと感じました。
自治会長 長澤

短歌コンクールを開催しています~自治会~
自治会では短歌コンクールを開催しています。
沖縄サテライト校(沖縄女子短期大学内)の学生も参加し、今回は62首の応募があり多くの学生の参加がありました。お昼休みの放送研究部による学内放送で短歌募集の案内をしたり、朝の勉強会の企画を工夫して実施しています。
次回の 第30回 学部・大学院 短歌コンクール
お題は 「大谷翔平さん」です。
第29回 学部・大学院 短歌コンクール 秀歌発表
お題は 「あなたにとって短歌三十一文字とは」
☆最優秀歌【一席】
デジタルアーカイブ専攻 2年 伊藤 ひよりさんが受賞しました。
視野広げ 魂込めて 綴る文字 三十一文字の 真実なりて
【講評】短歌に向かう心、三十一文字に向かう意識は、それは毎日の5限の授業の生活から目と心を離れさせるものである。句作は、昨日・今日、そして明日を思わせる時であり、我が魂と向き合っているときである。出てくる言葉が、我が姿を映し出している、と。まことにその通りであると、共感しました。書きたい言葉のある生活づくり、これからに期待します。(教授 森洋子)
リーダー研修会を行いました
学生自治会主催によるリーダー研修会を3月29日に行いました。各部活動の26団体の代表者が参加し、令和4年度の部活動の計画や部活動ごとの抱負、コロナ禍での活動方法の確認をしました。
杉山理事長、松川学長、冨士学生部長の先生方のお話から学んだこと
・リーダーの仕事はしっかり学びながら責任をもって最後までやりきり、力を身につけることが重要。
・社会に出ると必要なのはコミュニケーション能力とリーダーシップ
・4年間を通して成長しなければならない。毎年成長した自分を見つめなおすことが重要。
全体を通して、ただやるだけではなく、自分たちで考えて、時には仲間とぶつかり合って、本気で取り組むことで、意味ある活動にしていくことが大切であると感じました。そして、その活動を率先して進めていくリーダーの立場である私たちは、誰よりも高い志をもって活動していこうと思いました。
令和4年度 自治会長

リーダー研修会を行いました
学生自治会主催によるリーダー研修会を9月21日に行いました。各部活動の約30団体の代表者が参加し、前期の活動を振り返るとともに、後期のコロナ禍における活動内容やさぎ草祭での活動内容を確認しました。全部活動を代表して、書道部に前期の活動実績を報告してもらいました。
杉山理事長、松川学長、冨士学生部長の先生方のお話から、
・SDGsの目標を達成できない国に手を差し伸べるために、何ができるのか、今までやってきたことが
本当に良いことなのか考えることがリーダーの役割である。
・なぜマスクをするのか、なぜ消毒をするのか、理由を考えた上で感染予防に努めることが大切
・コロナ禍でどのように活動していくのか考え部員を先導していくことがリーダーの務めである
以上のことを学ぶことができました。
後期はさぎ草祭も控えているため、部活動同士が交流できる場を設けることは大切だと思いました。リーダーとして、様々な面にアンテナを張り、意識して生活することが求められると思いました。 自治会長
自治会学生による教育研修会~自治会~
4月5日(月)に入学式後に部活動紹介、6日(火)に学内にて新入生教育研修を行いました。
部活動紹介では、私たち自治会役員が学校での活動の紹介と計26団体の部活動が新入生に向けて部活動紹介を行いました。
新入生教育研修では、自治会による先生紹介や上級生との交流会を行いました。上級生交流会では、各学科専攻の上級生が新入生に授業の取り方や、授業で必須のIT講習、学校生活でわかっていると便利な事を教えることができ、相談会を行いました。昼食時間は県人会ごとに分かれ、十分にコロナ対策を行った上で同じ出身県の上級生や同級生と共に昼食をとり、今後の県人会活動の説明をしました。
多くの人に相談できる機会を得て、また大学の様子を知ることができ、新入生の緊張が少しでも和らぐことができた教育研修になったのではないかと思います。
会長 金沢真裕