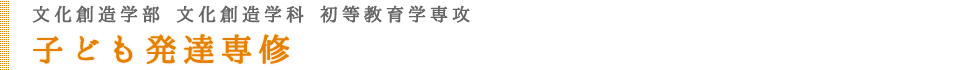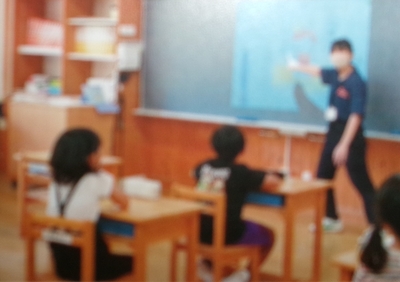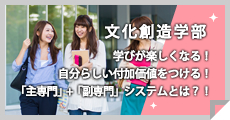オープンキャンパス
6/9(日)のオープンキャンパスでは、今話題の「メタバースの教育利用」について学びます!
インターネット上の仮想空間「メタバース」を教育で活用する動きが進んでいます。そうした中、6月9日のオープンキャンパスでは、メタバースをどのように活用するのが効果的かを理解し、実際にメタバース制作を体験することを目的とした授業を行います。
今後、メタバースの活用の広がりが予測されます。メタバースについて理解するよい機会となります。デジタル技術を活用した教育に関心のある人は、是非ともお越し下さい。
5月19日(日)のオープンキャンパスは、教育実践力を高めるEGGプランの紹介!
5月19日(日)のオープンキャンパスの体験授業テーマは、「大学ではどんな体験学習ができるの?ー先輩から学びの過程を教わろう!」です。
初等教育学専攻では、各学年でそれぞれ保育実践や教育実践を積み上げていきます。実践と理論を学びながら教育実践力を高める「EGGプラン(Enjoy Grow Growing up)」の保育者・教育者の養成について紹介します。
きっと参加することによって、岐阜女子大学に入学してからどんな講義を受けるのか、どんな活動があるのか、わくわく・ドキドキと大学生活への具体的なイメージができる思います。
先輩の体験談では、学生が4年間で力を入れてきたことや、成長してきたと感じることについても話をします。是非、大学生活の不安なことや知りたいことについて、尋ねてみてくださいね。高校生の皆さんの参加をお待ちしております。
写真は、昨年度4年生の遠地体験学修の様子です。子どもたちの前に立つ機会をたくさんもちながら、4年間かけて仲間と切磋琢磨していきます。
4月28日のオープンキャンパスは、プログラミング学習体験!
初等教育学専攻では、未来社会を生き抜いていく力を子どもに身に付けることができる保育者・教育者になるよう、教育DXと体験活動に力を入れています。
4月28日のオープンキャンパスでは、教育DXについて、実際にどのように小学校の授業で進めているかの一端を知っていただきます。小学校で実施されているプログラミング的思考の育成をめざした授業とは何かを学ぶとともに、実際の授業でも使われている教育用マイコンボードmicro:bitを使ってプログラミング体験学習を行います。幼児教育に関心のある人も、デジタル技術について学んでいくことで、幼児期の子どもにできることを考える機会になります。
オープンキャンパスに参加することにより、新しい教育の実際を学んでいただく機会になるとともに、本学での学びを教員や学生から具体的に聞くことができる時間を設けていますので、本学での学びについても理解する機会にもなります。皆さんの参加をお待ちしております。
3月23日のオープンキャンパスは?
オープンキャンパスでの体験授業のタイトルは、「保育も教育も、先生の言葉がかぎ。先ずは『言葉』を学ぼう」です。
保育園・幼稚園、小学校・中学校での保育・教育において言葉は欠かせません。私たちの日常生活においても同様です。そこで、今回は、その「言葉」について考える機会を設けました。
皆さんと大学生との言葉のやりとりから、「心地よい言葉のかけ方」について、実感して学びます。また、自分の言葉かけについて診断もしてもらいます。言葉を使って話すことが楽しいと思える活動を用意しています。
春の訪れをいっぱい感じることができる岐阜女子大学へのお越しをお待ちしています。ミニイベントでは、今話題のメタバースについて、体験的に学ぶこともできます。今回のテーマは、「メタバースに小学生の学びの部屋を造ろう」です。メタバースについて学ぶよい機会にもなります。一度体験してみませんか。
岐女大で、最新の教育方法を取り入れた学びを体験しませんか!
8月20日のオープンキャンパスでの体験授業では、今、世の中で注目を集めているメタバース(仮想空間)を自分たちが創る体験をしていただきました。教育においても、メタバースが学びに活用できます。たとえば、離れた地域の児童生徒同士が一緒に学ぶ合うことができます。また、体が思うように動かせなかったり、教室で仲間と一緒に学習することが一時的に出きなかったりする児童生徒も、メタバース内でアバター(自分の分身)として自由に動き、学びを行うことができるのです。このように、新しい技術を活用することで、学びの世界が大いに広がります。
本学では、最新の教育方法を取り入れた学びを行っています。9月18日のオープンキャンパスや10月15日のオープンキャンパス(大学祭)でも、メタバースを体験できます。一度、メタバースを体験してみませんか。