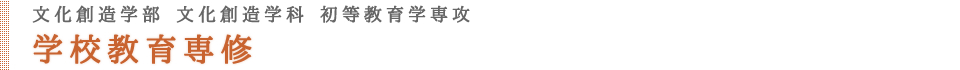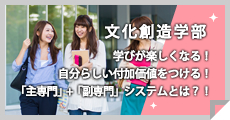農業研究会活動
"心みたい" ~さつまいも収穫~
「わぁ!大きい!」「僕の掘ったお芋見て~!」10月14日、今まで育て続けていたさつまいも畑に子どもたちの歓声が響きました。最初は一つのバケツに収まるほどの小さな苗から土の中で育ち、大きなさつまいもへと成長していく姿に学生も子ども達も感動しました。
さつまいもは、一つも同じ形はなく、それぞれ個性をもっています。大きくてでこぼこしたもの。小さいけれど、同じ苗からいくつも実っているもの。掘ってから見える一つひとつの姿に「すごい!」という新鮮な感動が味わえるのだと思います。
そしてその感動は子どもの素の言葉として現れます。
「心みたい」と例えた子どもがいます。
周りの赤紫色の根っこを血管で、さつまいもが心に見えたそうです。
また、「にんじんみたい」と例える子もいました。だんだんと細長くなる姿を見てそう思ったそうです。
このように、子ども達は、初めて出会ったさつまいもを見て、生き物として捉えたり、今まで自分が知識としてもっていることと照らし合わせたりして、〇〇みたい、と比喩する力がつくことができるのだと学生も学びました。
さつまいも掘りはただ楽しいだけではなく、子ども達に対して様々な感動や感性を刺激し、体験をもった確かな知識となるのだと分かりました。
次回のさつまいもパーティーでは、今まで自分が育てた体験を振り返りながら秋のおいしさを味わいたいと思います。
幹部 学校教育専修2年 飯田花純(富山県立呉羽高等学校出身)

〈予想よりもずっと奥まで土中に伸びて、大きく育っていることに驚いていました〉

「このさつまいも、心みたい」

〈あんなに小さかった苗も、ずっしりした重さに〉

〈収穫したさつまいも。形や大きさをジッと見比べていました〉
ビックリする程大きくなってる!~さつまいも観察会~
9月28日に子ども達と観察会行いました。子ども達と私達が一緒に活動するのは今回が2回目になります。
今回の観察会では、さつまいもの成長を子ども達と予想してから畑に移動し、実際にみることで自分の予想よりもはるかに大きくなっていて、「ビックリする程大きくなってる!」と教えてくれました。人間が大きく成長するにはとても時間がかかりますが、さつまいもをはじめ植物の成長はとても速いという、自分との『違い』にも目を向けれたと思います。また、「さつまいもを自分の子どものように大切にしよう」という約束のもと、水やりを行ったり、自分の背とつるの長さを比べる事で、さつまいもの成長に目を向け、普段体験できない事から気づき・発見をする事が出来ました。
今回私は司会として、子ども達と多く関わりを持たせて頂きました。夏休み中にあった保育実習の経験をもとに、子どもが分かりやすいキーワードを決めて前に立つ事で子ども達が集中して取り組める様に出来ました。しかし、自分の反省としてもう少し自分の言葉で子どもの心に刺さるような事を伝えるという事等があります。
次回のさつまいも掘りや今後の活動を通して、子どもの生きる力の基礎を育むお手伝いや、自分達のスキルアップが出来るように取り組んでいきたいと考えています。
子ども発達専修2年 芳村夏奈(長野県大町岳陽高等学校出身)
9月28日に子ども達と共に、サツマイモの観察会を行いました。6月1日の苗植えから約3ヶ月経ち、子ども達にとってサツマイモの成長を肌で感じられる活動になったと思います。観察会を始める前、子ども達に「苗はどのくらいの大きさだったかな?」や「どういう風に植えた?」と聞き、前回の活動を思い起こすことで、サツマイモの成長や学びを深められることができたと思います。また、サツマイモに対し優しい気持ちを育てられるよう、「サツマイモにとってみんなはお母さん」という話をし、開式のあいさつをしました。
畑では、大きくなったサツマイモの葉と蔓をかき分け入っていく子ども達と学生が一緒になって、水やりをしたり、新たな発見を共有したりしました。一人一人違った反応を見せる子ども達と共に学生の顔も生き生きとしていました。
サツマイモの葉に絵を描く活動では、それぞれが好きな葉を選び、すごく集中して、絵を描いていました。子どもにとって柔らかい葉は力加減が難しく、しかし手で押さえながら丁寧に描く姿が印象的でした。破れてしまった子どもへの前向きな声かけがもっと上手くなりたいと思いました。
一年生は積極的に子ども達に声かけをし、お互いが笑顔になる活動を心がけ、二年生は実習で学んだことを生かして子ども達と関わっていました。
しかし、「すごいね」や「大きいね」などの声かけは出来るものの、子ども達の「学び」に繋がる声かけが少なかったと感じました。例えば「葉の裏と表で色が違うよね」や「どうしてこんなに蔓は広がっているのだろう。それは、たくさん光を集められるようにだよ」と子どもに考えさせる問いかけができたら良かったなと思いました。このような「学び」に繋がる声かけを心がけ、お互いにとって充実した学びになれるよう取り組んでいきたいと思います。
今回の観察会は私達にとっても大きな学びとなり、次に生かすためのヒントを得ることができました。子ども達も終始集中し、笑顔が溢れた活動だったと思います。サツマイモに優しく接し、生き物の大切さを改めて感じられる、子供の心を育む観察会をこれからも続けていきたいと思います。
学校教育専修2年 寺嶋彩花(愛知県立大府東高等学校出身)

「私の身長よりもこんなに大きいよ」
 「根元に水をかけるために、成長した蔓をかき分けるのは力がいるよ」
「根元に水をかけるために、成長した蔓をかき分けるのは力がいるよ」

「さつまいもの葉っぱはうちわみたい。涼しい?」
〈紙とは質感の違う、葉に絵を描く活動〉
〈葉に絵を描いてバッチにしました〉
「こんなにちいさなカタツムリを見つけたよ」

稲から学んだ教師力 ~稲刈り~
9月20日、農業研究会の学生の稲の収穫を行った。
研究会では、将来教師・管理栄養士・親になったときに生かせる学びを得ようと日々活動している。
9月10日に田んぼの半面の稲を収穫し、はさがけまで行ったが、乾燥しすぎてしまい、米の水分量が11%になってしまった。最適な水分量は約14%であるので、米の品質が下がってしまった。前回の収穫では反省点が残った。
この失敗を今回の収穫ではしてしまわないよう、反省点を生かして残り半面の収穫に取り組んだ。予定では3日後の収穫(台風の影響があれば8日後)の収穫を考えていたが、稲の成長と台風の影響を考慮し、早めの収穫にした。
自然に合わせて自分たちが動かなければいけないことを実感し、いつも口にしている食料は、このように自然に合わせて農家の方が働いてくださっているからあるということを学び、これをしっかり子ども達にも伝えていきたいと感じた。
さらに環境に合わせて対応するという点は教師になったときの様々な対応と重なるところがあると考えた。その時の出来事に瞬時に対応していくことは教育現場でも同じであるので、臨機応変に動けるようになりたいと痛感した。
今後の脱穀や籾摺りなどの活動でもその時に応じた動きが取れるよう心掛け、さらなる学びを得ていけるよう励んでいこうと思う。
学校教育専修2年 大橋春奈(静岡県立静岡東高等学校出身)

豊年エビ大量 発見!~先輩から受け継いだ農法で田植え~
4月30日に播種を行った苗も、ようやく11cmの大きさまで成長しました。順調に芽出しができ、すくすくと大きくなった苗に対し、日光や水を与えるタイミングを誤り、一部の苗を枯れさせてしまった思わぬ状況に涙しました。苗は私たちにとって、ただの植物ではなく、育てている子どものような存在です。
▼枯らしてしまった苗から学んだことをクラスに置き換え▼
苗:ミュージカルや部活で忙しくてもこまめな水やり、観察が必要
→クラス:他の仕事より何より子どもが一番優先、細かいところにも気を配って子どもを見る、守る
苗:資料に書いてあることだけではダメ、その年の気候に合わせる
→クラス:毎年同じ子どもではないから、同じ方針で学級経営できるわけではない、問題解決できるわけではない
そうしたことを再確認し、教員となる日を夢見ながら愛情をもってこまめに世話をしました。ようやく今日5月25日に田植えを迎えることができ、水田に植えられるまでに成長した苗には、「育ってくれてありがとう」と胸が熱くなります。これからは水の管理を丁寧に行い、苗の成長を見守ります。
また、透明で朱色の尾をもち、仰向けで泳ぐホウネンエビをたくさん見つけました。別名タキンギョ(田金魚)やナエキンギョ(苗金魚)とも呼ばれ、ホウネンエビ(豊年蝦)が大量発生する年は、豊作になると伝承されています。
お腹に卵を保持したホウネンエビも多数見られ、他にも、5mm程のオタマジャクシ、2cm程のゲンゴロウ、水グモ、アメンボ、イトトンボ、お掃除屋のガムシの幼虫など様々な生き物の姿がありました。
これらも生き物の姿が見られるのも、周囲の機械を使用している水田と比較して見ても、私たちの水田のみです。これまで機械を入れずに手作業で稲作を進めた、先輩方の苦労が実を結んだ気がして、とても嬉しく感じました。
そして、私たちが高校生だった時に、生物の授業で唾液腺を調べた染色体の実験で懐かしい、ユスリカ幼虫も見られました。これらは、クモ類が捕食し成長の大きな助けになると言われています。稲作では、殺虫剤を散布して水稲害虫を防ぎますが、もともとこれら害虫はクモ類が捕食します。こうした食物連鎖を学び、生態系を整え、農薬を使わない方法もあります。私たちはこれからも、栄養あるお米作りに励んでいきたいと思います。
農業研究会幹部2年 伊澤知織(静岡県立韮山高等学校出身)

〈手作業での代掻きを重ねた水田〉

〈ホウネンエビ〉

〈横縄植による田植え〉
生きるための学び~代掻き~
私達が、これから親や教師として子ども達と接する中で、「食」について伝える場面はとても多いはずです。そんな時、「食べ物の命や大切さ」「農家さんが苦労して作っている事」など、誰にでも言える情報では子ども達の印象には残りません。印象的で且つ、生活や学習に活かせるようにするには、教える自分達が実際に身体を使い学修することで、子ども達に『生きた知識』を伝えられると考えました。その学修の1つとして、稲作活動を行なっています。
4月27日に、18人のメンバーで大学付近の水田にて、代掻きを行いました。
朝早くからの活動でしたが、全員で代掻きを行う理由を確認し、来て下さった先輩方から、アドバイスをいただきました。そのお陰で、「いつも触れる土」と「水を含んだ土」の感触の違いに驚き、「どうしてクモは水の上を歩けるのか」や「表面の泡みたいなものは何だろう」などの疑問を持つ事が出来ました。メンバー一人ひとりが、今日の活動を通して、自分なりの学びを発見出来たと思います。
今回代掻きを行なった効果として、今後の田植えがしやすく、稲の発育が良くなることだけではありません。それぞれが抱いた疑問や発見を共有したり調べたりする事により、学びがより一層深まります。そして、自分にしかない『知識』という武器を蓄えることが出来ます。
これから数多くの経験を積み、疑問を知識にする事が出来る活動を全員で創り上げて行きたいと思います。
農業研究会幹部 初等2年 芳村夏奈(長野県大町岳陽高等学校出身)