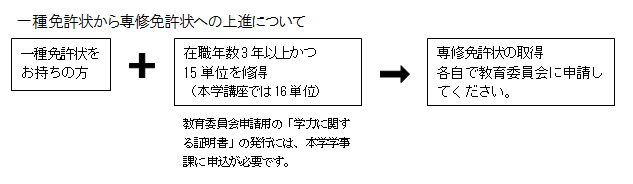令和7年度 大学院科目履修講座
幼稚園・小学校教諭専修免許状(対面講座)
幼稚園教諭専修免許状および小学校教諭専修免許状取得のため学習の機会を提供することを目的としています。
開講科目・日程
| 授業名 | 単位 | 日程 | 申込必着日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育実践特講Ⅰ~初等教育~ | 2 | 5/18(日)、6/1(日)、6/29(日) | →5/15(木) |
| 2 | 教材開発特講~初等教育~ | 2 | 5/24(土)、6/7(土)、7/5(土) | 5/15(木) |
| 3 | 遠隔教育特講 | 2 | 5/25(日)、6/15(日)、7/6(日) | 5/15(木) |
| 4 | 教育相談研究 | 2 | 8/23(土)、8/24(日)、8/30(土) | 8/14(木) |
| 5 | 教育経営特講 | 2 | 10/18(土)、10/19(日)、10/25(土) | 10/9(木) |
| 6 | 教育方法特講Ⅱ~初等教育~ | 2 | 10/26(日)、11/9(日)、11/30(日) | 10/16(木) |
| 7 | 教材開発研究~初等教育~ | 2 | 11/1(土)、11/15(土)、11/22(土) | 10/23(木) |
| 8 | 学校経営特講~初等教育~ | 2 | 11/2(日)、11/23(日)、11/29(土) | 10/23(木) |
時間割について
授業時間割りについては、次のとおりです。
1科目は1限(90分)×15回の授業です。
| 1限 | 9:20~10:50 |
|---|---|
| 2限 | 11:00~12:30 |
| 昼休憩 | 12:30~13:10 |
| 3限 | 13:10~14:40 |
| 4限 | 14:50~16:20 |
| 5限 | 16:30~18:00 |
初日受付9時~
おことわり
- 講師または、その他やむを得ない事情により日程等が一部変更になることがあります。
- 受講申し込み者数が一定数に達しない場合、開講を中止にする場合があります。
- 以前に単位認定を受けている科目は受講することが出来ません。
※「教育方法特講」について
「教育方法特講Ⅰ~初等教育~」(令和6年度開講)と「教育方法特講Ⅱ~初等教育~」(令和7年度開講)は、別科目の扱いになります。
※対面講座と通信教育で同一の科目を受講することは出来ません。
(例:対面授業の「教材開発特講~初等教育~」(5/24、6/7、7/5)を受講した場合、
通信教育の「教材開発特講~初等教育~」は同一科目の為、受講できません。
対面講座と通信教育で同一の科目を受講することは出来ません。
(科目名が変更になっている場合を含む。不明な場合は事前にお問い合わせください) - 各科目、初日に教材販売(2,000円程度)を行う場合があります。
市販テキストの事前購入をお願いする場合もあります。 - 1科目から申し込みは可能です。
但し、複数回にわたり申込された場合、受講料の振込手数料がその都度発生します。
講座詳細
会場
| ①岐阜会場 | 岐阜女子大学サテライトキャンパス文化情報研究センター 岐阜市明徳町10番地 杉山ビル |
|---|---|
| ②沖縄会場 | 岐阜女子大学沖縄サテライト校 沖縄県島尻郡与那原町東浜1番地 沖縄女子短期大学内 |
受講料について
受講料は1科目(2単位)15,000円です。(教材代別途)
受講対象者
令和7年度内に本講座にて開講する科目は、幼稚園教諭1種免許状または小学校教諭1種免許状を有し、教職経験年数3年以上で専修免許状に上進する方を対象に開講しています。
(教育職員免許法別表3)
単位認定について
授業は原則として、土・日曜日を利用した講義です。5分の4以上の出席が必要ですので、1日欠席されますと単位認定ができません。
お申込みについて
お申込みの流れ
①受講のお申込み→②受講確認書・振込依頼書到着→③受講料のお振込み→④講義を受講
①受講のお申し込み |
申込みは、下記の申込フォームより行ってください。 申込フォームはこちら |
②受講確認書・振込依頼書の到着 |
申込受付後にEメールにて、受講確認書・振込依頼書が届きます。 お手元に届きましたら、お申込み内容に誤りがないか、ご確認ください。 |
③受講料のお振込み |
受講料(1科目15,000円×受講科目数)を1週間以内にお振込みください。 振込手数料は、各自でご負担願います。 |
④講義を受講 |
入金確認後の連絡はしません。開講日に会場にお越しください。 |
学力に関する証明書の申し込み方法
学力に関する証明書の申し込み方法・申込書のダウンロードはこちら
証明書は代金引換郵便(証明書発行料、郵送料、代引手数料含む)で発送いたします。
申し込み方法の詳細をご確認の上、
申込書に必要事項を記入し、FAXまたは郵送でお申込みください。
※電話によるお申込みは受け付けておりません。
問い合わせ先
授業概要
1.教育実践特講Ⅰ~初等教育~
多様化する社会からの期待に応えるために、様々な現代的教育課題を取り挙げ、その実践等を学び、中・高等学校における教育実践についてさらに深く追究する。中・高等学校教育の場が求める教育者として、教職の基礎及び中・高等学校の教科等に関する専門的知識に基づく実践的指導力を学修し身につけ、教育者の専門職としての自覚とその教育を効果的に進めるための理論と実践力をさらに深く追究する。
加えて近年課題となっている情報通信技術(ICT)を活用した学びの方法なども子どもの発達段階に応じた方法を追究し、その実践力の向上を図る。
2.教材開発特講~初等教育~
教材及び学習指導方法の現状と課題を理解する。また、教材開発に必要な学習指導要領・指導目標・学習の状況、課題解決など学習活動の様態を理解し、そこで活用できる教材開発を実践的に行う。また、中・高等学校でのインターネット等、新しいメディアを活用した教材開発と教育方法の事例を学習し、それらの特徴を把握する。教材開発の改善に役立つ学習の評価方法について理解する。
3.遠隔教育特講
教育DX(Digital Transformation)時代における"新たな学び"とは,教師がデジタル技術を活用し,学びのあり方やカリキュラムを革新させると同時に、教職員の業務や組織、プロセス、学校文化を革新し、時代に対応した教育を確立することである。また、学びという側面から考えてみると教育DXの目的は、「個別最適な学びという"新たな学び"の実現」である。20世紀の学習観は,行動主義・認知主義の学習観を採用していた。しかし,21世紀に入り、学習観は「主体的・対話的な深い学びの実現」という構成主義・社会構成主義の学習観に移行した。この変化から分かるように、教育が「全員に同じ教育」から「個々が持つ能力を最大限活かす教育」に変化している。ここでは,教育DX時代における 遠隔教育という"新たな学び"の在り方について考える。
4.教育相談研究
教育相談機能を高めるために、基礎的な知識・技術を習得する。具体的には、心理療法の各理論やアセスメントの方法を学ぶ。また、カウンセリングの理論と技法を学習する。さらに、中等教育の現場の課題である、いじめ、不登校、発達障害、非行・怠学、自傷行為など問題行動の理解と支援について学ぶとともに、危機対応と心のケア、および予防的関わりとして、学級づくりや教育相談システムについて習得する。
5.教育経営特講
教育のしくみとして「公教育」を、教育の歴史的な背景や流れとして「教育政策と学校教育」を、そして、今日学校教育の運営の中で取り組まれている「マネジメント」を取り上げ、この3つの視点から学校における教育活動の運営や経営を探求していく。こうした学びをとおして、教育活動やその運営を動かしている「考え方」を見いだし、そこから、教育実践の意味、教育の方法の在り方を問い直すこととする。
6.教育方法特講Ⅱ~初等教育~
教育方法は、学習者の発達に応じた柔軟な実践力によって展開される。それは教師の臨床的で実践的な固有の特徴と深く関わる。この視点から、特に中・高等学校段階における授業の設計、教材の開発、授業の方法、授業の技術、授業の評価・改善を教師の授業認知力をコアに、自分の授業から学び取ることについて研究し考察する。さらには新たな教育メディアを活用した授業方法を修得する。
7.教材開発研究~初等教育~
学校でのCAI、CMI等の情報化の歴史的な発見を理解し、教材に関する情報のデジタル化教材と教育利用の検討を進め管理メタデータの教材・素材の情報源、学習環境、知的財産権、プライバシー、個人情報の取り扱いについて考察し、教材デジタルアーカイブの作成が可能になるように学習する。各教科のデジタルアーカイブを用いた教材化について、デジタルアーカイブの教育利用についての実践を理解する。
8.学校経営特講~初等教育~
今日の学校は、いじめや不登校、学級崩壊といったこれまでにも指摘されてきた問題に加え、ゆとり教育の見直し、「主体的・対話的で深い学び」の導入、ICTの活用といった新たな課題への対応が求められている。一方、改正教育基本法の教育理念の下、学校・地域社会・家庭が連携して生徒の「生きる力」を育むことが求められており、次期学習指導要領では「社会に開かれた教育課程」を重視するとともに、その理念のもとで学校が絶えず教育課程を見直し、教育活動の改善・向上を図る「カリキュラム・マネジメント」の実現が求められている。本講義では、これらの背景を踏まえ、これからの学校経営の在り方について、多面的な視点から検討する。
一種免許状から専修免許状の上進について
免許法施行規則第6条別表3 (実務経験を活かしての上進)