垂井子ども歌舞伎 岐阜・西濃地方 不破郡岐阜・西濃地方

| 連絡先 | 垂井町教育委員会 | TEL | 0584-22-1151 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 上映時間 | 5月1~4日(本楽4日) |
アクセス方法
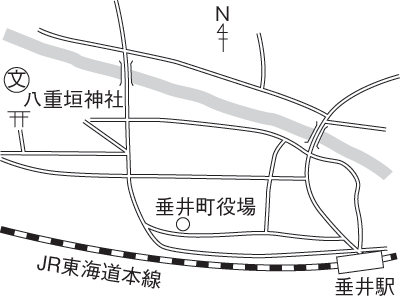
JR東海道本線垂井駅より徒歩8分
解説
(1)歴史・沿革
文和2年(1353)北朝の後光厳天皇が当地に御逗留の折、天皇安泰祈願として里人が花車3台を造って曳き廻し御慰めしたという曳起源の伝承がある。現在の3輌について、東町の鳳凰は寛政10年(1798)作、西町の攀鱗閣は文化5年(1808)作、中町の紫雲閣に関連しては安永4年(1775)歌舞伎上演の記録があり、その後、各曳は絢爛豪華な装飾を施されると同時に舞台として改造・完成されていったと思われる。子ども歌舞伎の上演は、中町資料により安永年間とされている。「垂井曳まつり」は町のほぼ中心部に位置する八重垣神社の例祭で、子ども歌舞伎はこの祭礼の奉納芸となっている。
(2)見所・特色
祭礼本楽(5月3日)の午前、3町内から役場へ集合し、3町一緒に八重垣神社までの「古式練込み」がおこなわれる。役者の子ども達を中心に、一番を先頭に公演関係者一同が行列を作り、神社まで行進する。あでやかな役者姿の子ども達には、沿道の観衆から感嘆の声が上がる。午後、神社境内に整列した曳の一番が先ず「三番叟」と歌舞伎を奉納し、それに続いて二番・三番が順に奉納する。役者は、それぞれの町内の男子小学生のみである。三町の競うが如き熱演が見ものである。
(3)上演に向けて
師匠としての振付師を中心に、2月初旬に始動、本格的な練習は4月以降である。声の出し方、所作を安定させるための腰の位置、視線の方向、身のこなし等々時には厳しく時には優しく、各師匠の指導は三者三様だが入念に行なわれる。そこから子ども達は、4日間(5月1日の足揃え・2日の試楽・3日の本楽・4日の後宴)で10回以上の上演に耐え得る芸を身に付けていく。
(4)子ども歌舞伎と地域の願い
役者としての子どもだけではなく、師匠・家族・町内住民、特に一番神事係の青年達の絶大な尽力と総合力が結実した公演である。子ども達も、歌舞伎の面白さだけでなく、師匠をはじめ大勢の人々との信頼関係・地域との連帯感を心に築き上げていく。それは親の願いであり、地域皆の願いでもある。
 |
 |
| 稽古風景 | 軕を収納する蔵 |











