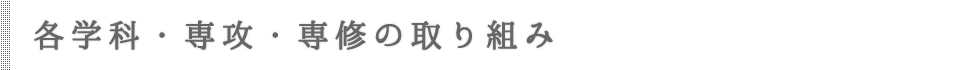教員情報
| 学部・学科 | 文化創造学部 文化創造学科(Faculty of Cultural Development) |
|---|---|
| 職種 | 助教 【修士】 |
| 氏名(カナ) | スズキ リカ |
| 氏名(漢字) | 鈴木 里香 |
研究分野(field of study)
保育内容
研究テーマ(Research theme)
保育現場における幼児の発達と小学校との接続
研究実績一覧(Research Publications)
論文・資料作品等(Papers Material works)
| 表題 | 単・共著 | 刊行 | 概要(共著者名) | 関連授業科目 |
|---|---|---|---|---|
| 稲作と教員養成~教師を目指す学生や小学校教諭へ~ | 共著 Co-author |
遠隔教育振興会NO.2,令和6年2月 | 教育者を目指す岐阜女子大学初等教育学専攻の学生が取り組んできた稲作実践について、作業工程や各教科との関わりを体系的にまとめたテキストを制作。(共著者:杉山博文) | 生活科基礎、初等教科教育法(生活) |
| 幼児が自然の変化を知るための稲の成長の教材化 ~発芽から収穫までのデジタル・アーカイブ~ | 単著 single author |
岐阜女子大学カリキュラム開発研究Vol.5,No.1,pp97-106 | 幼児が最も日常的に体験している食生活、その中でも米食は、多くの家族の主食となっている。幼児は食生活での体験と稲とは結びついていない。そこで食生活の基本的な米と稲との結びつき、さらに、稲の発芽、田植え、稲刈り、脱穀までの稲の変化と人々の努力のプロセスを記録し、幼児に季節の時々の状況を提示する教材を作成した。また、幼児の食、身近な稲の成長、掲示等による自然の変化を受け止める力の育成に役立つ教材化の在り方を検討した。 | 保育内容(環境)、保育内容(人間関係)、生活科基礎、初等教科教育法(生活) |
| 教育の地方分権に対する木田宏の指摘と課題 | 共著 Co-author |
岐阜女子大学文化情報研究2024,Vol.26No.1,p.17-26 | 戦後の教育委員会制度は、第一次米国教育使節団や連合国の司令部によって与えられたものであり、日本の分断政策であると反対意見が多かった。地域の人々と学校を結びつける重要な機能としての教育委員会制度に対する木田宏の指摘とその課題を明らかとした。(共著者:杉山博文) | |
| 個人学習の自動化のレベル6の分類と実践の課題 | 共著 Co-author |
岐阜女子大学文化情報研究2024,Vol.26No.2,p.54-58 | 教育改革が進められてきたが、現在はまだ個別学習を集団学習の補助的傾向にある。OECDが6つのレベルに分けた個別学習の自動化より検討を行い、今後、社会の理解、経済、行政、教育的価値観から、完全自動化の導入を検討すべきである課題を明らかとした。(共著者:後藤忠彦・杉山博文・熊﨑康文) | |
| 教育デジタル化による教育実践の行動カテゴリーの再検討~パターン認識、AI等の新しい処理システムの活用の基礎として~ | 共著 Co-author |
岐阜女子大学文化情報研究2024,Vol.26No.1,p.7-16 | 今後、人工知能ロボット等の発展により、短時間で多くのデータ分析が可能となることから、教育のデジタル化による行動カテゴリーの再検討を行った。(共著者:眞喜志悦子・横山隆光・齋藤陽子) | 生活科基礎、初等教科教育法(生活) |
| 学習の理解度、積極的参加、ウェルビーイングの授業分析からの教育実践資料のデジタル化の考察, | 共著 Co-author |
岐阜女子大学文化情報研究2024,Vol.26No.1,p.1-6 | 現在、AI、パターン認識等のデータ処理を用いた分析・提示の方法の開発が進もうとしている。今後のAI、パターン認識、知能ロボットの基礎となる実践資料の理解度、積極的参加、ウェルビーイングの観点から、データ化および問題点を検討した。(共著者:眞喜志悦子) | 生活科基礎、初等教科教育法(生活) |
| 小麦栽培活動を通して学ぶ自然と共生した食農保育の実践 | 共著 Co-author |
岐阜女子大学紀要第52号p95-99 | 農業研究会が主催する農業子ども活動に参加することを通して、害獣の被害を経験することで自然の厳しさを経験したり、自生している植物を収穫し自然の恩恵を受けたりする経験は「命は自然のなかで育つ」という認識を子どもたちのなかに育てることが示唆された。そして保護者も子どもが得た感動や発見を一緒に分かち合うことで、家庭における食生活もより豊かになることが期待された。 | 保育内容(環境) 初等教科教育法(生活) |
| 幼児教育の機能語の学習について小学校1年生の教科書の活用からの考察 ~幼児の日常の言語活動を小学校算数から見た必要性~ | 共著 Co-author |
岐阜女子大学カリキュラム開発研究Vol.5,No.1,pp37-42 | 過去の教育資料等を活用し,幼児期における機能語(用語と用語を結びつけ,論理的な思考操作をする言語)と小学校1年生での機能語の利用状況およびその後の指導で論理的な思考操作が必要とする算数の教科等での利用状況から幼児教育における機能語の活用の意識化の必要性について考察した。(共著者:眞喜志悦子・松川禮子) | |
| 保育者養成課程の学生と保育者養成課程以外の学生が共同で実施するミュージカル活動に関する意識Consciousness Regarding Musical Activities Conducted Jointly by Students in the Nursery School and Those Ooutside the School | 共著 Co-author |
岐阜女子大学カリキュラム開発研究2020.3 Gifu Women's University Curriculum Development Research,3.2020 |
保育者養成課程の学生のみで実施した場合と,保育者養成課程の学生と保育者養成課程以外の学生が共同で実施した場合でのミュージカル活動に関する意識は変わらなかった。学生はミュージカル活動の意義を理解しており、職業の選択やコミュニケーション能力などの向上と関連付けているものと思われた。(共著者:土井のぞみ・中島法晃・奥村正彦・横山隆光) |
保育内容(身体) Preschool Education (Activities) |
| 保育者養成女子大学のミュージカル活動に関する学生の意識 Student's Consciousness about Musical Activity pf a Nurture Person Education Woman's University |
共著 Co-author |
岐阜女子大学カリキュラム開発研vol.3No.3,2018.12,p25-32 Gifu Women's University Curriculum Development Research,Vol.3 No.3,12.2018,pp.25-32 |
保育者養成女子大学の学生に、ミュージカル活動実施後、共同作業認識尺度、動機づけ自律スタイルなどに関する意識調査を実施した。アンケートの分析から学生は、人間関係を良好な状態に維持することなどを活動の動機とし、ミュージカル活動は自律的忍耐力を養ったり満足感や達成感を得たりするものと感じていることが分かった。ミュージカル活動を総合表現と捉え、各専門領域の基本的な知識・技能の習得を前提として、授業内容を充実させる必要がある。(共著者:土井のぞみ・奥村正彦・横山隆光) | 保育内容(身体) Preschool Education (Activities) |
| 特別の教科道徳で用いる情報モラルに関わる題材の内容 Contents Related to Information Morals Used in Special Subject Morals |
共著 Co-author |
岐阜女子大学文化情報研究2016,Vol.17No.3,p.15-22. Gifu Women's University Cultural Information Studies 2016, Vol.17 No.3, p.15-22. |
情報モラルに関する題材を扱う場合の留意点を明らかにした。(共著者:横山隆光・吉村希至) Clarify points to keep in mind when dealing with information morals. |
学校経営特講 Special Lecture for School Administration |
| 中学校特別の教科道徳で情報モラルに関する題材を扱う際の課題 Issues when Dealing with Information Morals in Junior High School Special Subject Morals |
共著 Co-author |
日本教育工学会第32回大会講演論文集,平成28年9月,pp.193-192. Proceedings of the 32th Annual Meeting of the Japan Society for Educational Technology,2016,pp.193-194. |
実証授業を行い中学校特別の教科道徳で情報モラルに関する題材を扱う際の課題について調査した。(共著者:横山隆光・加藤直樹・興戸律子・及川浩和・山崎宣次・笠原康弘) We conducted a demonstration class and investigated the problems when dealing with information morals in junior high school special subject morals. |
学校経営特講 Special Lecture for School Administration |
| タブレットPCの持ち帰りによる情報モラルの授業と道徳の時間の連携 Coordination of Moral Time with Information Morals Classes by Taking Tablet PCs Home |
共著 Co-author |
日本教育工学会第31回大会講演論文集,pp425-426. Proceedings of the 31th Annual Meeting of the Japan Society for Educational Technology,2015,pp.425-426. |
小学校道徳科で情報モラルに関する題材を扱う場合、タブレットPCを家庭に持ち帰って学習に利用する際の留意点について明らかにした。(共著者:横山隆光・加藤直樹・興戸律子・山崎宣次・及川浩和) In the case of dealing with information morals in elementary school morals, we have clarified the points to keep in mind when taking a tablet PC home for learning. |
学校経営特講 Special Lecture for School Administration |