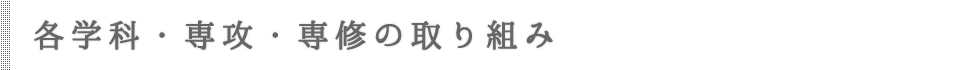教員情報
| 学部・学科 | 文化創造学部 文化創造学科(Faculty of Cultural Development) |
|---|---|
| 職種 | 教授【学士】 |
| 氏名(カナ) | オクムラ マサヒコ |
| 氏名(漢字) | 奥村 正彦(Okumura Masahiko) |
研究分野(field of study)
乳幼児保育
研究テーマ(Research theme)
・非認知能力を高める保育者のかかわり
・幼児期の終わりまでにつけたい力
研究実績一覧(Research Publications)
論文・資料作品等(Papers Material works)
| 表題 | 単・ 共著 |
刊行 | 概要(共著者名) | 関連授業科目 |
|---|---|---|---|---|
| 幼保小の連携・接続に関する考察ー「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」に視点をあててー |
単著 Single author |
岐阜女子大学紀要Vol.54号,2025年2月28日,pp35-45 | 平成29年に改訂された幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(以下「10の姿」と表す)が示された。幼稚園・保育所での「10の姿」の活用の現状を把握したうえで、幼保小の連携・接続の一層の推進を図るための幼児期における「10の姿」の生かし方の案を示した。 | 保育原理 保育者論 |
| 幼保小の架け橋プログラムに関する調査研究事業 ~接続期カリキュラム開発サポートシート(言語)作成~ |
単著 Single author |
令和5年度岐阜県カリキュラム開発会議ワーキンググループの言語領域担当 | 岐阜県は、文部科学省の「幼保小の架け橋プログラムに関する調査研究事業」を受託し、幼保小の連携・協働に架け橋プログラムの開発・実践の一環として、接続期カリキュラム開発サポートシートを作成した。ワーキンググループの一員として、言語領域の執筆にあたった。 | 保育原理 幼児と言葉 |
| 幼保小の連携・接続に関する考察ー小学校の取組に視点をあててー A Study on Cooperation and Connection between Kindergartens and Nursery Schools and Elementary Schools -Focusing on the Efforts of Elementary Schools- |
単著 Single author |
岐阜女子大学紀要Vol.53号,2024年2月28日,pp25-34 Faculty of Cultural Development, Gifu Women's University Received November 10,23 25-34 |
平成9・10年頃、「小1プロブレム」が全国各地で顕著になった。この現象を契機として、幼保小共に様々な取組がなされたものの、令和4年3月、文部科学省が「幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き」を作成し、カリキュラム・教育方法の改善等を求めてきた。そこで、自身の経験を基に、小学校長経験者へのアンケートも活用して幼保小の連携・接続について振り返ったうえで、幼保小の円滑な接続に不可欠な取組・道筋を小学校の立場から取りまとめたものである。 | 保育原理 保育者論 |
| 『乳幼児期に育みたい「自己肯定感」に関する考察ー調査を通してー』 Consideration on Self-affirmation that We Want to nurture In Infancy and Early Childhood -Through Research- |
単著 Single author |
岐阜女子大学紀要Vol.52号,2023年2月28日,pp69-77 | 日本の若者の自己肯定感が低いことは、1990年代から危惧されており、保育者にとっても自己肯定感を育むことが課題の一つととらえる。乳幼児期に自己肯定感を育むためには、愛着理論の重要性を理解し、実践することが基盤となる。そこで、保護者・保育者に愛着・自己肯定感に関するアンケート調査を実施し、分析することを通して、保護者・保育者が共にエビデンスに基づく養育・保育の必要性を認識し、実践することの重要性・課題を示すことができた。 | 乳児保育 保育原理 |
| 遊びや生活の中で非認知能力を育む在り方 | 単著 Single author |
岐阜女子大学紀要Vol.51,pp65-73 | 非認知能力は幼児期に顕著に発達し、学力向上や社会で活躍する鍵となる重要な能力である。その非認知能力を幼児期の遊びや生活の中でどのように育むとよいか、実践してきたことをもとに提案している。さらに実践したことを保護者評価により、妥当性について述べている。 | 保育原理 幼児と環境 |
| 乳幼児期に人と関わる力を育むための在り方~園長としての実践を通して~ Ideal way to deverop the power to interact with people in infancy ~Through practice as a principal~ |
単著 Single author |
岐阜女子大学カリキュラム開発研究Vol.5,No.1,pp83-90 | 1980年代から顕在化してきた人間関係にまつわる諸問題の原点は乳幼児期にあるとも言われている。乳幼児期の子どもたちの生活・遊びの中で、どのように人と関わる力を育むとよいのか、発達過程をふまえながら、指導構想をもち、具体化を図ることが必要である。6年間を見通した指導構想をもち、計画的、継続的に指導していくことが重要であることを確認できた。 | 幼児と人間関係 |
| 子どもの成長に資する人的環境としての園長としての在り方 The Idea way of the Director as a human Environment that Contributes to the Growth of Children |
共著 Co-author |
岐阜女子大学カリキュラム開発研究Vol.5,No.1,pp21-28 | 「子どもにとっての最大の環境は人である」と言われるほど人の存在は大きなものがある。保育園長として保育に関わる中で、人的環境としての園長の在り方についてしていくことにより、追究ことにより、子どもの環境への関わりを深め、豊かな体験を得るためには、間接的な役割とともに直接的な役割があり、人的環境としての園長は両面を重視することが必要であることを示すことができた。(共著者:鈴木里香) | 幼児と環境 保育内容「環境」 |
| 生活習慣の確立を図るための構想と指導の在り方~園長としての実践を通して~ Concept of Design and Guidance for Establishing Lifestyle Habits ~Through Practice as a Principal~ |
単著 Single author |
岐阜女子大学紀要Vol.50,2021.2,pp73-81 Bulletin of Gifu Women's University No.50 February 2021. |
保育所保育指針において、乳幼児期での基本的生活習慣の形成の重要性が記されている。そこで、園長として、保育に携わる中で、乳幼児期に必要な生活習慣を身に付けているための在り方を明確にし、実践に努めた。その結果、6年間を通して、適時性、一人一人の違いをふまえて、計画的、継続的に指導・援助していくことの有効性を示すことができた。 | 幼児と健康 |
| 「子どもの学びや心を育む図書に関する検討~絵本から主題を読みとる分析を通して~」 Consideration about the book which brings child,s leaning and heart up Gifu Women,s College bulletin Co-author |
共著 Co-author |
岐阜女子大学紀要Vol.49,2020.2,pp53-58 Bulletin of Gifu Women's University No.49 February 2020. |
子どもの学びや心を育む視点から、絵本の主題に関する読み手の側からの調査・分析を行い、図書資料の検討を進めた。これにより、それぞれの絵本の内容や表現から読みとれる主題の特徴が明らかになった。(共著者:吉村希至・松井徹・竹本茜) The purpose is to clarify the characteristic subject that can be read from the contents and expressions of the picture book in the examination when selecting the picture book. From the viewpoint of nurturing children's learning and mind, the reader side regarding the subject of the picture book By condcting a survey and analysis from,the characteristics of the subject that can be read from tha contents and expressions of each picture book were clarified. |
幼児と環境 Environment and Cultural Activities |
| 保育者養成課程の学生と保育者養成以外の学生が共同で実施するミュージカル活動に関する意識 | 共著 Co-author |
岐阜女子大学カリキュラム開発研究Vol.4 No.1,2019,pp55-60 Gifu Women's University Curriculum deveropment research 2018 Vol.3 No.1 |
保育者養成課程の学生と保育者養成課程以外の学生のミュージカル活動に関する意識に差はなく、学生はミュージカル活動の意義を理解しており、ミュージカル活動を職業の選択やコミュニケーション能力などの向上と関連づけているものと思われる。(共著者:鈴木里香・土井のぞみ・中島法晃・横山隆光) Consciousness about musical activity of a student of a nurture person education course and a student besides the nurture peason education course is impatial ,and a student seems to understand the significance of the musical activity and relate musical activity to vocational choice and improvement of communiction ability. |
教職リサーチⅠ Teaching researchⅠ |
社会貢献(Social contributions)
| 概要 | 備考 |
|---|---|
| 岐阜市第4回「コミュニティ・スクール推進セミナー」に市橋小学校学校運営協議会コーディネーターとしての立場から発表 | ①2001年度から始めた「市橋子育てプログラム」の継続・実践に努めること。 ②学校の教育活動と地域の活動・人とつなぎ、学校の教育活動の支援・充実に努めること。 ③学校の課題に対し、共に考え、解決に努めること。 の3点を話した。 |
| 子育てコラム(令和3年度 JA共済連岐阜 子育てに関する情報発信 無料通信アプリLIN公式アカウント「JA共済こそだてひろば(岐阜県))」の11月号・2月号) | 子育て世代を応援するための子育てに関する情報発信を目的とした「子育てコラム」(JA共済こそだてひろば 岐阜県)の11月号・2月号を担当。11月号には、「3歳までの子どもへの関わり方」、2月号には、「乳幼児期に育みたい非認知能力」についてそれぞれ4回、述べた。 |
| 岐阜市地域多文化共生推進員としての活動...地域における日本住民と外国人住民との交流及び共生に関すること、外国人住民の地域活動への参加の促進に関すること、地域における多文化共生の意識の啓発に関することについて、会議(6回)で意見を述べたり、実際に地域で活動したりした。 (2018.9.1~2020.3.31) | 岐阜市地域多文化共生推進員として会議において主張したことは、①日本に在籍する期間の異なりに応じた関わりの必要性②行政・自治会役員の役割の明確化③地域の実態に合った活動の構想づくり・推進 等であり、岐阜市市民参画部国際課の多文化共生施策・推進の参考となった。 |
講演(Lecture)
| 表題 | 主催 | 概要 | 関連授業科目 |
|---|---|---|---|
| 土岐市「幼保小の架け橋プログラム」研修会(土岐市は幼保小の架け橋プログラムに関する研究調査地区) | 2024.9.2 土岐市研修会 | ①「10の姿」を幼児教育と小学校教育の共通言語として育てたい子ども像を明確にすることで、子どもの育ちの連続性を図りたい ②小学校低学年では、幼児教育で身につけたことを生かしながら教科等の学びにつなぎ、子どもたちの資質・能力を伸ばすこと。そのために、小学校教員は幼保この子どもたちの活動をよく観察し、学びの実態を把握することが不可欠であること。その折、保育者は、子どもの学びの芽生えの具体の発信に努めることが重要であることなど を話す。 | 保育原理 保育内容総論 |
| 「幼児期の学び」について考える ~幼児教育の質の向上を求めて~ | 2024.1.31 大津市立保育園・幼稚園合同研修会 | 「幼児期の学び」について考えることを通して、幼児教育の質の向上を図ることを目的として、幼児期に育みたい資質・能力について理解し、育み方について考える。幼児期の学びの観点から、今までの実践を振り返り、今後の在り方を明らかにする。 | 保育原理 保育者論 |
| 令和4年度公開講座「自己肯定感を高め、意欲的に取り組む子ども」 Children who raise their self-affirmation and work enthusiastically |
ネットワーク大学 コンソーシアム岐阜 | 日本の若者の自己肯定感の低さが指摘されている。予測困難な時代を生きていく子どもたちにとって自己肯定感を高めることが幾多の困難に立ち向かい、充実感のある生き方をしていくことにつながるのではないか。そのために、自己肯定感を高める在り方について追究した。 | 保育原理 保育者論 |
| 令和3年度公開講座「今一度3歳児神話について考える」 Think again about the myth of a 3-year-old child |
ネットワーク大学コンソーシアム岐阜 | 3歳児神話とは「子どもが3歳になるまでは母親は子育てに専念すべきであり、そうしないと成長に悪影響を及ぼすという考え方である。その考え方に合理的な根拠は認められないものの3歳になるまでの子育ての重要性と母親以外の子育ての関与の重要性について述べた。 | 乳幼児保育 幼児と人間関係 |
| 令和2年度公開講座「今一度3歳児神話について考える」 Think again about the myth of a 3-year-old child |
ネットワーク大学コンソーシアム岐阜 | 3歳児神話とは、「子どもが3歳になるまでは母親は子育てに専念すべきであり、そうしないと成長に悪影響を及ぼす」という考え方である。この考えに合理的な根拠は認められないものの、3歳になるまでの子育ての重要性と母親以外の子育ての関与の必要性について述べた。 | 保育原理 乳児保育 |
| 平成26年度岐阜県中堅保育士研修会 Heisei 26 Gifu Mid-lebel nursery teacher training |
岐阜県保育研究協議会 | 常磐保育園の保育理念・保育目標・育みたいこと・各クラスの取り組みについて説明した。育みたいこととして5つ(①思いっきり遊ぶことができる子②基本的な生活習慣が身についた子③いろいろなことに挑戦する子④友だちと楽しく生活ができる子⑤自分の思いを表現できる子)をあげ、発達段階をふまえながら6年間を通して援助していくことが大切であることを話した。 | |
| 平成29年度保育士養成施設の学生のための研修 Training far students at the Heisei 29 Nursery school training |
岐阜県保育研究協議会(県の委託事業) | 0~5歳児の6年間で育みたい力として非認知能力が重要であることを話す.保育の魅力を子どもの姿を通して伝える。 I talked abut the importance of deveroping non-cognitive abilities and the attractiveness of childcare through the concrete appearance of children in the 6 years of 0 to 5years old. |
|
| 平成30年度岐阜市第2回学びの部屋教育活動サポーター研修会 Heisei 30 Gifu City's 1st Room Education Activity Supporter workshop |
岐阜市教育委員会青少年教育課 | 子どものやる気を引き出すために、子ども一人一人をよく把握し、認め、ほめることの重要性について実践をもとに話す Through concrete efforts,I talked about the importance of understanding,recognizing,and complimenting each child in order to motivate them. |