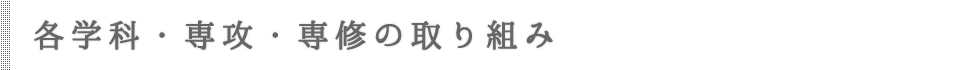教員情報
| 学部・学科 | 文化創造学部 文化創造学科(Faculty of Cultural Development) |
|---|---|
| 職種 | 教授(博士) |
| 氏名(カナ) | カワハラ トシアキ |
| 氏名(漢字) | 河原 俊昭 |
研究分野(field of study)
英語教育
研究テーマ(Research theme)
・言語政策と英語教育法
・観光英語の効果的な指導法
・外国人住民への言語サービス
研究実績一覧(Research Publications)
論文・資料作品等(Papers Material works)
| 表題 | 単・ 共著 |
刊行 | 概要(共著者名) | 関連授業科目 |
|---|---|---|---|---|
| Diversity & Inclusion をめぐる大学英語教育の課題と実践 | 共著 Co-author |
『JACET中部支部紀要 第19号』pp.77-100 | DiversityとInclusion という言葉が今後の社会を読み解くキーワードとして注目されている。英語教育においてもこれらの概念が必要であることを述べて、それに対応した授業法について考察をしている。 | 英語科教育法Ⅰ、Ⅱ |
| 外国人住民を日本社会にどのように迎えるか | 単著 Author |
『都政新報』2022年2月15日,pp.8 | 外国人住民が日本社会に増えている中で、日本社会では、差別とか格差が生じないような形で迎入れることで、望ましい多文化多言語共生社会が生まれゆく。 | 在留外国人と言語 |
| 自治体サービスと言語的マイノリティ | 単著 Author |
『都市問題 vol.112』 後藤・安田記念東京都市研究所, 2021年11月,pp.50-58 | 外国人労働者が増えるにつれて、地方自治体がどのようにして彼らの言語問題を取扱いつつあるか、また言語サービスの特徴がどのように変化しつつあるか述べている。 | 在留外国人と言語 |
| 英語の文末焦点と文末重点 | 単著 Author |
『テクニカルレポート Vol.6 No.1』 岐阜女子大学デジタルアーカイブ研究所,2021年6月,pp.16-19 | 英語の情報構造の視点からの考察である。新情報が集まる文末を、文末焦点と文末重点の二つの視点から考察して、その共通性を探っている。 | 英語学概論 |
| 外国人集住都市の言語問題 Language Problems in the Localities with a Concentrated Foreigner Population |
単著 Author |
『日本語学 vol.37-9』 明治書院,2018年,pp. 56-65 Japanese Linguistics vol.37-9. Meiji Shoin |
外国人集住都市会議に参加している都市(美濃加茂、豊田、浜松など)において、急増する外国人の子どもたちに対してどのような日本語指導が行われているか分析をしている。 I investigate how the Japanese Language is taught to increasing foreign children living in Minokamo-city, Toyota-city, Hamamatsu-city and so on. |
|
| 言語政策 ー国際比較の観点からー Language Policies - in terms of international comparison - |
共著 Co-author |
『英語教育徹底リフレッシュ: グローバル化と21世紀型の教育』開拓社,2017年4月,pp.142-152 Refreshing English Education. Kaitakusha |
言語政策について概論をのべて、そのあと各地域、ヨーロッパ、アジア、日本とその特殊性と共通性をのべて、そこから多言語社会における言語政策のあり方について述べる。(共著者:今尾康裕ほか(編)) We investigate the language policy in general and then examine local areas, such as Europe, Asia and Japan. We consider their specialities and commonalities of language policies in multilingual societies. |
英語科教育法 Methodology for English Education |
| 東南アジアの英語 ーフィリピンとマレーシアの事例からー English in Southeast Asia - Focuing of the Philippines and Malaysia - |
共著 Co-author |
『国際理解42号』 帝塚山学院大学国際理解研究所,2016年9月,pp.125-8 Global Understandings. Tezukayama-Gakuinn University |
フィリピンとマレーシア両国における英語の状況を社会言語学的視点から考察している。両方の英語とも、English as a Second Language として、World Englishes の広がりの中で、どのような状況下にあるか考察している。 An analysis of English situations concerning the Philippines and Malaysia in terms of the sociolinguistic point of views. |
英語学特講 Special Lecture for English Lingusitics |
| 英語音声の効果的な指導について ー指導の順番に関する考察ー Effective Ways for English Pronunciations |
単著 Author |
『カリキュラム開発研究 2016 Vol.1, No.2』 岐阜女子大学カリキュラム開発研究所,2016年12月,pp.19-24 Curriculum Develpment Studies Vol.1 No.2. Gifu Women's University |
初等英語教育を担当する場合、どのように教えたらいいのか、その教授法や指導の順番を考える。 I examine the method and order of English education in the primary education. |
英語の音声 English Phonetics |
| フィリピン the Republic of the Philippines |
共著 Co-author |
『国際的にみた外国語教員の養成』東信堂,2015年5月,pp.109-122 Training of Foreign Language Teachers from the International Viewpoint, Toshindo |
各国で外国語教員の養成がどのように行われているか考察して、日本の現状との国際比較をした。そして、どのような点を学べるか考察をしてある。(共著者:大谷泰照・杉谷眞佐子・橋内武・林桂子(編)) We examine how foreign language teachers are trained in other countries, and also compare those systems internationally. |
英語科教育法 Methodology for English Education |
| 外国人高齢者への言語サービス Language Services for Foreign Senior Citizens |
共著 Co-author |
明石書店,2015年2月,pp.64-79 Akashi-shoten |
杉野俊子・原隆幸(編)『言語と格差』に執筆する。日本に増えてきている外国人高齢者のために、どのようなサービスが必要か、特に言語サービスの視点から論じている。 We consider the possibility of providing language services to increasing foreign senior citizens. |
|
| 英語教育の行方 The Future of English Education |
共著 Co-author |
大阪教育図書,2015年3月,pp.135-190 Osaka Kyoiku Tosho |
英語教育の今後のあり方について考えた提言をまとめた京都光華女子大学・英語英米文学会(編)の論文集である。(共著者:木戸・Wright・Drayton)(担当部分:「小学校の英語教育から考える英語教育」) We have shown several suggestions on future English language teaching systems in Japan. |
英語科教育法 Methodology for English Education |
| 国際化時代の言語文化 Language and Culture at the Time of Globalization |
共著 Co-author |
大阪教育図書,2013年5月,pp.21-72 Osaka Kyoiku Tosho |
大学での英語教育の経験からその授業改善へのいくつかの提言をまとめた京都光華女子大学・英語英米文学会(編)の論文集である。(共著者:工藤・Drayton・木戸)(担当部分:「英語教育の到達目標としてのTOEICとCEFRの有効性の考察」) From our experiences, we present several suggestions for improvement of English education systems. |
英語科教育法 Methodology for English Education |
学会発表(Presentations)
| 表題 | 主・ 分 |
発表 | 概要(共著者名) | 関連授業科目 |
|---|---|---|---|---|
| 「多文化共生力を育成する大学英語教育」 | 第63回Jacet国際大会愛知大学(名古屋キャンパス),2024年8月29日 | 多文化共生化が進む現代において、英語教育の在り方もその変化を意識したものにかわるべきである。具体的には従来の英米英語に特化した英語を教えるのではなくて、国際英語への視野も含めるべきである。つまり、英語の多文化、国際共通語化への視点を持つべきである、ことを論じている。 | 在留外国人と言語 | |
| 「ChatGPTを用いた英語教育の可能性」 | ALR・辞書プロジェクト会議 | 学生の間に、ChatGPTの使用が普及するにつれて、従来型の英作文(自由作文、課題作文も含めて)の指導が困難になってきている。今後は、英語教育の場において、ChatGPTを排除するのではなくて、有効に活用しながら、学生の英作文能力を向上させたいと考えて、そのいくつかの試みを発表した。 | 英語科教育法Ⅰ | |
| 「英語教育における多義性の包摂と無自覚な特権」 | 日本応用言語学会 in 大学英語教育学会 学術交流集会 | 英語教育において、英語という特権的な言語を扱うことによって、教える側も教わる側も、知らず知らずのうちに特権的な立場に無意識に属することの危険性を提起している。さらに、英語教育でありながらも、言語教育一般への展望を広げることが、多義性の包摂へとつながることを述べている。 | 英語科教育法Ⅰ | |
| ポスター発表「大学生の多文化共生意識に関する量的及び質的研究」 | 応用言語学会 in 大学英語教育学会 | 現代日本は多文化共生社会と言われているが、それに関して学生に意識調査を行った。はじめは、アンケート調査であるが、アンケート調査だけでは分かりづらい個々の考えを、インタビューを繰り返すことで、把握しようとした。本発表では、量的と質的の両方から行ったアプローチの結果を踏まえて考察を述べている。 | ||
| 「多文化共生社会と言語教育」in JACET Hours 「英語教育とDiversity Inclusion―多様性を包摂した新しい英語教育への提言」 | 大学英語教育学会(オンライン発表),2021年8月27日 | 多文化社会へ向かう現代において、英語を学修することによって、どのように意識が変化するかアンケート調査している。それによって、多言語社会への寛容度がたかまり、共感性も深まると述べている。 | 英語科教授法 | |
| 口頭発表「地方大学における『観光英語』の授業のあり方について」 | 2019年科研費合同研究集会,早稲田大学,2019年2月15日 | オリンピックを迎えて、増大すると予想される外国人観光客への対応のために、各種の観光サービスの充実が行われている。東京だけではなくて、地方でもその必要性は強いを思われる。対応する、地方の教育機関でおこなわれる観光英語の授業の在り方について考察した。 | ツーリズムイングリッシュ Tourism English |
|
| 「外国人高齢者に関する言語サービス」(平成23年度科学研究費補助金、基盤研究C研究、研究成果報告書、課題番号 23520706) 研究分担者 Language Services for Foreign Senior Citizens sponsored by the National Research Funds |
Assistant-Researcher | 『日本におけるマイノリティー言語に関する実態調査と言語支援開発』pp.43-59 Research and Language Supports for Minorities in Japan |
日本に増加する外国人高齢者が言語的な問題のために十分な支援を受けられていない実態を明らかにするとともに、どのようにシステムを変えていくことで、支援が可能になっていくか考察した。(共著者:斉藤早苗(編)) We find that foreign senior citizens do not receive enough language supports. To deal with this problem, we consider how we can support those people. |
社会貢献(Social contributions)
| 表題 | 発表 | 概要 | 関連授業科目 |
|---|---|---|---|
| <講演>言語政策と地域日本語教育 Language Policies and Japanese Language Education in Localities |
浜松版地域日本語教師養成講座,2016年10月8日 Programs for Training for Japanese Language Teachers in Hamamatsu |
浜松は外国人集住都市であり、日系ブラジル人の多い都市である。そこで日本語を教える教師たちに、言語政策の視点からどのような問題点があるか講演をした。 Hamamatsu-city is one of "Localities with a Concentrated Foreigner Population." In that city, I made a lecture about what is the current problmes in terms of language policies. |
テキスト(Text)
| 表題 | 単・ 共著 |
刊行 | 概要(共著者名) | 関連授業科目 |
|---|---|---|---|---|
| An Invitation to Critical Thinking(クリティカル・シンキングのすすめ) | 共著 Co-author |
南雲堂,2015年11月,pp.7-12,37-42,61-66,73-78 Nanundo |
学生に英文を読みながらクリティカル・シンキングの考えを理解してもらうために編纂された大学生用のテキストである。(共著者:高垣・斉藤・Wright・木村) We edit and publish a textbook which will provide students how to understand a method of critical thinking. |
英語 English |
| Hospitality English(おもてなしの観光英語) | 共著 Co-author |
三修社,2015年11月,pp.6-9,14-17,26-29,42-45,54-57 Sanshusha |
オリンピックを見据えて外国人観光客の増大が予想されるので、日本人が外国人観光客を日本各地へ案内するという前提で編集された大学生用テキストである。(共著者:木戸・Wright・徳地) We write a textbook for the studens who will guide foregn tourists at the time of the Olympic Games. |
ツーリズムイングリッシュ Tourism English |
| 英字新聞で学ぶ異文化理解 Cross Cultural Understandings through English Newspapers |
共著 Co-author |
英宝社,2012年11月,pp.7-18,24-29,36-41 Eihousha |
英字新聞Daily Yomiuri誌の記事を読むことで、異文化理解を深め用とするテキストである。(共著者:石川・小宮・徳地・吉川) We edit a textbook for students who are interested in cross-cultural understandings by reading Daily Yomiuri. |